こんにちは。ハーラン・エリスンが亡くなったそうですね。
TwitterのTLで、早川書房さんから、「悲しいニュースをお伝えします」とか流れてきたんですけど、わたしは別に悲しくはなかったです。もはやいいお年で、新作をそんなに書いているわけでもなし(こないだ短編集の翻訳が二冊出ましたけど古いやつです)、そもそも翻訳がまったく出ていませんがなんか事情があるんでしょうか、日本の原稿料が安いからとかいう話もありますけど、ほんとなんですかね? あ、”Can & Can’tankerous” は2010年あたりの作品を集めたものらしいので、面白いんだったら読んでみたい。というのも、「世界の中心で愛を叫んだけもの」などはたいへん冷戦的な話ですから、エリスンが9.11以降、どんな話を書いたのかという点にはいささか興味があるわけです。(とはいえ、英語で読むほどの気持ちはない。)
というわけで、今週はずっとエリスンについてなんか書こうとしていたんですけど、そしたらこんどは歌丸師匠もお亡くなりになられたそうで、こちらはエリスンとは違っていささか悲しいニュースかもしれません。つまり、歌丸師匠の芸は、彼が現に生きていることと切り離せないわけですけど、小説家の死は、その死がなにか彼の書いたものに関係あるかというと、すでにして書かれてしまった時点で作者と作品はあまり関係なくなっているわけで、つまり作者は書いた時点ですでにある意味死んでいるわけで、といったのはバルトですけど、今更実物のエリスンが死んだからといって、わたしにはあまり関係ないというか。
という話はさておき。エリスンといえば日本では長らく『世界の中心で愛を叫んだけもの』 “The beast that shouted love at the heart of the world”(短編集)が翻訳されただけで、雑誌でちょこちょこ翻訳されてはいましたが、長らく(40年ほど?)ほったらかしにされていたわけです。ですからわたしも、エリスンといえば「けものの人」としてしか知らなかったわけですが、「けもの」は大学生の時に初めて読んで、なかなか面白いと思いました。最初に読んだのはもう四半世紀前ですが、とくに「けもの」はことあるごとに読み返していたので、たぶんかなり好きな方なんだろうとおもいます。
というわけで、追悼の意をかねて、「世界の中心で愛を叫んだけもの」を解釈してみようと思います。14ページと短いものなので、読んだことない方は是非読んでみたらいいと思います。ハヤカワ文庫です。
あらすじ的なこと
いきなり解釈するのも不親切なので、まずはいちおうあらすじ的なことを書きます。読んだことある方はとばしてください。
題名にある「世界の中心」 “the heart of the world” とは、交叉時点 ”crosswhen” という場所(都市?)のことで、文字通りいろいろな時間線が交わる不思議な場所です。で、そこにさまざまな種族の代表による代表委員会があります。これが何を統治しているのかというと、狭義にはcrosswhen内を統治しているようですが、間接的には、crosswhenの「外」の時空にも影響を及ぼしているようです。具体的にはわかりませんが。つまり、crosswhenは、空間的にはともかく、時間的には文字通り世界の中心にあるといえます。
で、この世界の中心のある場所で、あるとき「気違い」が暴れて捕らえられます。(詳しくは書かれていませんが、たくさんの人を殺したようです。)「気違い」は七つの頭を持った竜で、「残存感情を浄化するために閉鎖されていた」レベルに潜んでいたのですが、そこで感情を探知するマシン(スペクター)から逃れようと思って、自分の感情を自閉させます。
気違いは最後のチャンスに賭けた。彼の心、七つの脳ぜんぶを、閉鎖したのだ。藤色レベルが閉鎖されたのと、そっくり同じように。すべての思考を閉ざし、感情の火を灰に埋め、心に動力を送る神経回路を切断した。(中略)思考に関するかぎり、竜は存在をやめた。スペクターは、そこに探知すべきなにものをも見出だせず、素通りしていった。しかし、気違いを追っている相手は正気で、彼のように狂ってはいなかった。彼らの思考は筋道立っており、そして、筋道立ったやりかたであらゆる事態を計算に入れていた。スペクターにつづいて、熱探知波が、質量計測センサーが、そして閉鎖レベルでも異分子の臭跡を狩り出すことのできる追跡装置がやってきた。(pp. 24-25)
というわけで、気違い竜は気づかぬうちに捕らえられてしまいます。
「気違い」をとらえるためのマシンは、第一にまずスペクターで、これはどうやら「気違い」の「狂気」を探知することができるマシンらしいです。で、「気違い」はそれから逃れるために、「無邪気」、「卑下」、その他、「九つの感情的偽装」をしたが無駄だったと書かれているので、要するに「狂気」というのは、「感情」の一種であるようです。
で、捕らえられた竜をどうするかという話になるわけですが、ライナという政治家が、センフという科学者に、竜を「排出」するように言い、センフは「排出」するのはもう少し待ってくれと言います。
「排出」というのは、竜から「狂気」を取り出すことらしいですが、その方法を開発したのはセンフです。で、ライナはcrosswhenの平和のために、竜から狂気を排出すべきだと主張します。
(センフ)「しかし、ほかのあらゆる生物、あらゆる場所、遠い遠い昔から、神のみぞ知るはるかなパララックスの彼方までにこれが及ぼす災厄を、考えてみろ。われわれは自分たちの塒(ねぐら)の汚染を取り除くために、これまでに存在したほかのあらゆる巣に犠牲を強いることになるぞ」
ライナは、しかたがないというように、両手を広げた。
「生存のためだ」
センフは疲労の色濃い表情で、ゆっくりとかぶりを振った。
「わたしだって、できることならあれを排出してしまいたい」
「できないのか?」
センフは肩をすくめた。「どんなものでも排出はできるさ。しかし、残されたものは、持つ価値のないものだろう」(p. 27)
crosswhenは時間の中心でもあるので、そこから外に竜の狂気を排出した場合、過去現在未来のすべてにわたって影響を及ぼしてしまうから、少なくともその影響がどこまで及ぶかを調べるまで、排出をちょっと待ってくれと、センフは言いますが、ライナはなぜかすぐにでも排出したがっています。
ここのところはなんかよくわからないのですが、どうもライナは、「排出」が具体的に何をどうすることなのかを、いまいち把握していなかったようにも見えます。というのも、ライナの立会いのもと、センフが竜の狂気を排出した後に、こんな会話をしているからです。
ついにタンクは満たされた。作動ステージの上には、ひとりの正常人が横たわり、目を閉じ、筋肉を無意識にひきつらせ、息をあえがせていた。
「排出は終わった」とセンフがいった。
「ぜんぶあのタンクにはいったんだね?」ライナが小声で聞いた。
「いや、全然」
「というと・・・・・・」
「あれは残り滓。無害だ。超感覚者のグループからとった試薬で、中和できる。危険なエッセンス、場を作っていた退廃性の力線――それらはもうない。すでに排出された」
ライナは、はじめて顔色を失った。「それらをどこへやったんだ?」
「聞かせてくれ、きみは同胞を愛しているかね?」
「おい、たのむよ、センフ! わたしはそれがどこへ行ったのか・・・・・・いつへ行ったのか、と聞いているんだ」(pp. 29-30)
竜から狂気を排出するに伴って、タンクになにか物質が満たされていき、タンクがいっぱいになったとき、竜は人間の姿になっていました。で、どうやらライナは「狂気」がそのタンクに満たされていると思っていたらしいのですが、それだったらそもそも最初にセンフが「よその世界のことを考えないのか?」とか聞いている意味が分からないはずです。なんかちょっとよくわからない部分ですね。あと、センフももうちょっとライナに詳しく説明しておいてやれよと思います。
で、その後、センフは、「わたしを許してくれるだろうね、ライナ。なぜなら、わたしも同胞を愛しているからだ。どこの世界、いつの時代に住む人びとをも。愛さなくてはいけない。こんな非人間的な分野にたずさわっていればこそ、よけいにそれに執着しなくてはならない。だから、わたしを許してくれるね」と言って、自分自身を竜と同じく排出装置にかけてしまいます。(センフの体はピラピラの紙みたいになってしまいます。)
竜の狂気を排出したことにより、さまざまな時間・世界に「狂気」が流入することとなり、現代のボルチモアに住むビル・スタログがスタジアムで銃乱射をしたり、五世紀のローマにゴート人やフン人が略奪をしかけたりといったことが起こります。
とはいえ、crosswhenにいる人たち(あるいは読者)には、「狂気の排出」→「過去・現在・未来にわたる外の世界への狂気の侵入」という二つの出来事の因果関係が把握されていますけど、外の世界の人たちにとったら、過去・現在・未来のすべてにおいて「狂気の侵入」があるわけで、それゆえ、「もともと世界はそういうものだった」という風に意識されているだろうと思います。
で、「狂気の流入」と並行して、センフが排出されたことにより、「狂気の流入」にところどころ切れ目が生じます。こんな感じ。
時空間と人びとの心を貫いて脈動してきた場。それが突如として不可解にも中断され、フン王アッティラは思わず両手で頭をかかえた。(中略)目にもやがかかり、それが晴れたとき、彼は胸の奥底からほっと吐息をもらした。アッティラは自軍に後退を命じた。(p. 31)
センフによる自身の排出は、どうやらライナに阻止されて、途中で中断されてしまったようですが、ある程度は排出されており、その結果センフはピラピラのパピルスのようになってしまいます。で、ライナはセンフが排出機構に過負荷を与えて機械を壊そうとしたと解釈して、センフの死刑を要求し、委員会はその要求を認め、センフに死刑判決が下されます。ライナの考えでは、センフがやったことは、crosswhenに「狂気の依然として跳梁する未来を与えようとした野獣的行為」だというわけで、委員会はそれを承認したということです。
ライナの立場は、crosswhenを狂気から守るというものですが、その正当性は、中心であるcrosswhenが狂気から守られていたならば、いずれ将来的には、その境界線(正気の領域)を外へと拡大することができ、外の世界も狂気から救われる日が来るかもしれないというところにあります。
そうした立場のライナに対して、死刑にされる直前のセンフは、
「きみは彼らのぜんぶに刑を宣告したようなものだ。狂気は生きた蒸気だよ。力だ。それをびんに閉じ込めることはできる。ただし、いちばん強力な悪霊を、いちばん栓の抜けやすいびんに閉じ込めるようなものだがね。そして、きみは彼らをつねにそれといっしょに暮らすことにさせた。愛の名においてだ」(pp. 33-34)
と言います。
それから、死刑になる人(政治犯?)は記念碑を建ててもらえるというしきたりがあるらしく、センフは自分のための記念碑を、自分のためにではなく、「彼らのために」建ててくれと頼んでから死刑になります。で、とある惑星に、大量虐殺をしてガス室での死刑判決を言い渡された瞬間のビル・スタログの銅像が建てられます。で、判決を言い渡された時のスタログのセリフ。「おれは世界中のみんなを愛してる。ほんとうだ、神様に誓ってもいい。俺はみんなを愛してる。おまえたちみんなを!」 題名の「愛を叫んだけもの」というのは、どうもこのスタログの叫びのことを言ってるようです。
で、最後に、かつてのシュツットガルトのとあるビルの残骸の中で、男が七色の箱を見つけ、それを開けたところ、「つむじ風」と、「翼を持った、顔のない黒いものの群れ」が飛び出して、その翌日、第四次世界大戦がはじまったという、パンドラの箱的エピソードがあって物語はおしまいです。
さて、以上があらすじですけど、あらすじだけ聞いてもわかんないでしょうから、未読の方はぜひ読んでみてください。この小説は、書き方が独特なのでとっつきにくいですけど、作品の構造はそんなに難しいものではありません。2~3回読めば理解できるかと思います。
わたしの解釈
というわけで、いよいよわたしの解釈を述べたいのですが、ネットで感想を漁ったところ、日本語しか見てませんけど、あんまり詳しく解釈している人はいないようでした。(SFの評論(紙媒体)などは、それこそもう20年ほど見ていませんのでよくわかりません。)
というわけで、せっかくなので少々詳しく解釈してみようと思います。
まず、わたしの解釈を、問いの形でまとめると次のようになります。読んだことがある方は、答えを考えてみてください。
① 狂気とはなにか?
② 愛とはなにか?
(ア) ライナにとっての愛
(イ) センフにとっての愛
③ 愛は世界の中心から外へと向かうが、中心は誰から愛されるのか?
それではわたしの答えを書きます。
① 狂気とは何か
話の発端は竜=気違いですが、彼はどうやらcrosswhenの中にいたものらしいです。彼の狂気は、「感情」のようなものらしいですが(スペクターで検出できるから)、それが「狂気」とされるゆえんは、おそらく、彼が七つ頭だということと関係があります。彼が捕捉されて監禁され、センフとライナを見上げた時に、
竜はふたりを見上げた。七重のイメージが見えた。
と書かれています。つまり、「正常な感情」とは、一つ頭による一つのイメージなのですが、それが「七重」であることによって「狂気」になるのではないかと思います。もちろん、ある一つの出来事に複数の意味があるのは正常なことです。ただし、そうした諸意味は、それぞれの人において、有力な意味を中心に構造化(統合)されているべきもので、まったく独立した7つの意味が並立しているという状態は、たしかに「狂気」といってよいのではないかと思います。
もちろん、七つ頭というからには、キリスト教的「七つの大罪」と関係があるだろうから、七つの大罪風に解釈してもかまわないんですが、七つの大罪というと、「高慢」「激情(憤怒)」「羨望」「堕落」「貪欲」「大食」「肉欲」のことですね。ちなみに、2008年に発表された新七つの大罪は、「遺伝子改造」「人体実験」「環境汚染」「社会的不公正」「貧困」「過度な裕福さ」「麻薬中毒」だそうです。ローマ教皇庁が発表したものだそうですが、新七つの大罪は、適当にその辺にある現代的で倫理的かもしれない問題を拾ってきただけのようで、哲学的基礎がないように思われます。
それはさておき、古典的な七つの大罪では、いわゆる「悪徳」とされるものがその内容になっているわけですが、(ライナはたぶんそう考えていると思いますが)、竜の「狂気」の正体を単なる「悪徳」としてしまうのは、少なくともセンフの考えではちょっと違うように思います。どうしてかというと、竜の狂気が排出された後に、竜は「正常な人間」になってしまうわけですが、それに対してセンフは、「残されたものは、持つ価値のないものだ」と述べているからです。
つまり、狂気が「七つの大罪」的なものだとして、そうした「悪徳」が取り除かれて「正常」な人間になるなら悪いことじゃないように思うわけですが、センフの考えでは、そうした「正常さ」は、少なくともそれだけでは「価値がないもの」だとみなされているわけですね。
それでは、「狂気」が単なる悪徳じゃないとするとなんなのか?
これはざっくりいうと、「対象(他者)に対するエモーション」のようなものだと思います。エリスンの作中で、直接的に「七つの大罪」が言及されているわけではないので、あんまり「七つの大罪」にこだわってもしょうがないですけど、せっかくなので七つの大罪をつかって考えると、七つの大罪とされる悪徳は、対応する美徳とセットになっています。それぞれ、高慢⇔謙譲、激情(憤怒)⇔慈悲、羨望⇔忍耐、堕落⇔勤勉、貪欲⇔寄付(清貧)、大食⇔節制、肉欲⇔純潔というように、悪徳と美徳が対になっています。
ざっと見てわかるように、悪徳とされるものは積極的な態度であるのに対し、美徳とされるものは消極的な態度であるように思われます。
例えば高慢と謙譲の対比は、「自己が他者に影響を及ぼす(高慢)」か、「自己が他者に影響を及ぼされる(謙譲)」かの対立だということですね。また、大食と節制、肉欲と純潔などの場合は、むしろ主になるのは悪徳の方で、美徳の方は「大食をしないこと」、「肉欲を持たないこと」というように、否定的にしか定義できなさそうな感じがします。(純潔はそうでもないかな?)
要するに、自他の関係において、生あるいは現世的な対象(他者)に積極的に(激しく・過度に)関わろうとする態度(エモーション)を悪い言葉で表現すると「七つの大罪」になり、そうした欲望的エモーションを抑制する態度をよい言葉で表現すると「七つの美徳」になるのだと思います。(いささか片寄った物言いだという異議は認めます。)
さて、「愛を叫んだけもの」において、竜の「狂気」とされているものは、具体的には他者を殺害したり、何かを破壊しようとしたりするエモーションのことで、これはもちろん、単純に「善か悪か」でわけるとすると、「悪」に相当します。その点では、ライナもセンフも同じ考えのようです。
しかしながら、狂気をcrosswhenから排出してしまえば、とりあえずcrosswhenの平和は保たれるし、それがひいては世界全体のために良いことだとするライナに対して、センフはそうは考えていません。
二人の立場の違いは、一見すると、
●大義(理念)のためにはある程度の非道は許される、つまり、全体のためには一部の犠牲は仕方がないという立場(ライナ)と、
●正しい理念(目的)のためだからといって、他者に犠牲を強いる等、正しくない手段をとってはいけないという立場(センフ)
の対立のようであり、その点から「どんなものでも排出はできるさ。しかし、残されたものは、持つ価値のないものだろう」というセンフのセリフを解釈すると、
●「正しい理念」のために不正な手段を使うとすると、「正しい理念」から「正しさ」が失われてしまうから、結果的に、「残されたものは持つ価値のないもの」になる。
という意味になりますね。(ソクラテスに、牢番を買収したから逃げてくださいといったら、死ぬのを避けるために死ぬ(精神的に死ぬ)ことはできない的な正論を言われて、なんだこいつ、みたいな話ですね。)
ただし、センフの考えは単にそれだけとも思えず、もう一段ひねりが加わっているように思います。というわけで、次の問題に進みます。
② 愛とは何か
(ア)ライナにとっての愛
ライナにとっての愛は簡単です。ライナにとっての愛は、最終的には「すべての生き物のために」、とりあえずcrosswhenを狂気から守ろうとすることです。最終的な目標のためには、一時的に外の世界の人たちに「狂気」を引き受けてもらうのは致し方ないという立場です。つまり、ライナにとっての「愛」は、感情ではなく、合理的判断だと言えるでしょう(本心からではないかもしれませんが)。
ライナにとって、「狂気」は「狂気」で、「正常」は「正常」、また、「愛」は「愛」であって「狂気」ではないわけですけど、彼が合理的だというのは、このように、各概念がそれぞれ自己同一性を持っていて、したがって必然的に彼の世界全体が合理的なものになっているという意味です。(「合理的rational」というのは、簡単に定義すると「一義的に言葉で言える」という意味です。)ですから、「crosswhen」と「その他の世界」は違うし、ライナが、中心であるcrosswhenの外の人たちを「劣った人たち」と見ているかどうかはわかりませんけど、少なくとも自分たちとは違う人たちだと見なしているとはいえると思います。
ライナにとっての「愛」とは、自分でも「生存のためだ」と言っていることからもわかるように、とりあえず、存在しているものを「殺さないこと」、なんであれ自己同一性を持っているものを「侵害しないこと」を指しているのだと思います。先ほどの七つの大罪との関係でいえば、「美徳」の方を重んじる態度であり、「美徳」と「大罪」は対立するものであり、まったく別のものだと考えるようなあり方ですね。(善悪二元論)
(イ)センフにとっての愛
ライナ的な「愛」に対して、「きみは彼らをつねにそれ(狂気)といっしょに暮らすことにさせた。愛の名においてだ」というセリフからわかるように、センフは批判的です。
それでは、センフにとっての「愛」とはなんでしょうか。
「排出後に残るものは持つ価値のないものだ」というセリフからは、センフが、(ライナが考えているような)単なる「正常な人間」であるだけではだめだという考えを持っているということが読み取れます。「狂気」的な部分を排出してしまうということは、人間性の重要な部分を喪失してしまうことになるのです。
もちろんセンフも、「狂気」をいいものだとは思っていません。しかしながら、同時に、「狂気」を単純に取り除いてしまえばよいものとも思っていないのです。
ビル・スタログは、「狂気」の影響を受けて、配達された牛乳に毒を入れてまわったり、飛行機に乗る母親のカバンにダイナマイトを仕掛けたり、スタジアムで銃を乱射したり、といった大量殺人を犯すわけですが、裁判にかけられ死刑を宣告されたとき、「おれは世界中のみんなを愛してる。ほんとうだ、神様に誓ってもいい。俺はみんなを愛してる。おまえたちみんなを!」と叫びました。これはもちろん、スタログが「愛を叫んだけもの」だということなのですが、センフにとっても、「狂気」は「愛」でないわけではないということを示しているでしょう。
ある側面からすると、スタログがやったことは、過激ではありますが、一種の愛であるといえなくもないわけですね。スタログ的な「愛」が対立しているのは、ライナ的な存在論です。つまり、自己同一性をもった存在者が、他者に侵されずにそれぞれが孤立して存在しているという状態にある場合、そうした他の存在者を「殺すこと」は、「愛」になりえないこともないということです。(めんどくさい言い方ですいません。しかしまあ、デリケートな問題なので、こういう言い方にならざるをえません。)
つまり、個々の存在者がライナ的な意味において「生きている=生存している=自己同一性を保持している」ということは、モナド論的に、それぞれが互いに孤立して存在しているということです。そこには「交流(コミュニケーション)」がありません。しかしながら、「生きる」ということは、他の存在者から孤立して存続することではなく、他の存在者と交流することであります。単に孤立して存続している状態というのは、たとえて言えば岩石のような無機物が存在するように存在しているだけであり、有機体の存在様態ではないという考えですね。有機体はものを食べる(他の有機体を殺して食べる)し、呼吸をするし、排泄をしますし、どんなものでもいずれは死にます。そうした「開かれた」あり方を「生きる」ことだとすると、ライナ的な「閉じた生」の「存続」は、「生」というよりはむしろ「死」に近いといえるわけです。(不死は生よりもむしろ死に近い。)
というわけで、ある視点からすると、孤立している存在者に穴をあけることは、スタティックな状態にある存在を、ダイナミックな状態にすることであり、他者とコミュニケーションするという意味では、「愛」であると言えなくもありません。渾沌に七竅を鑿つといったような感じです。
しかしながら、そのような「愛」は「狂った愛」であり、スタログや竜にとっては「愛」なのでしょうが、センフにとってはそうではないようです。(「できることならあれ(狂気)を排出してしまいたい」とか、影響を調べたいとか、もうちょっと待ってほしいとか言って排出にしり込みしたことからわかる。)
センフにとっての「愛」は、彼が自身を排出しようとしたことにおいて表現されています。
彼は排出法の考案者であるから、自身を排出することによってなにが起きるかはわかっていたと思います。つまり、センフの目的は、「狂気」の流入を、「数瞬、数年、あるいは数千年であったかもしれぬつかのま」、中断させることにあったと思います。(狂気の流入・排出を完全に停止することにではなく。ここのところが、わたしの解釈の独自性かなと思います。)
中心からの狂気の流入とは、「中心」と流入先の「外の世界」を二つの項と考えた場合、孤立していた二つの項をつなぐ「力動」だということができます。(「パララックス・センター交差時点(crosswhen)から吐き出された力線の場」、あるいは、「場を作っていた退廃性の力線」、あるいは、「狂気は生きた蒸気だよ。力だ」など。)
つまり、「中心」と「外の世界」は、中心から排出された「狂気」によってこそ、互いに関係しあうことができるということです。もちろんこの場合、互いに関係するといっても、中心から外の世界へというベクトルを持った動きであるわけですが。
しかしながら、二つの項の間の交通が可能であるのは、逆説的ですが、二つの項がそれぞれ別の項であり続ける限りにおいて(互いが自己同一性を保持し続ける限りにおいて)です。
ライナ的な「愛」だけでは交流がなく、個々の存在者は孤立したままです。それに対して、「狂った愛」はそうした他者と自己の境界線を突破しようとする力線です。しかしながら、「狂った愛」だけであるならば、今度は片方によるもう片方の破壊(殺害)によって、片方の項は項としての自己同一性を失ってしまいます。結果、「狂った愛」による他者の破壊は、最終的には破壊者の側の再びの孤立に至ります。つまり、ライナ的な孤立する愛が、それだけではだめなのと同様、「狂った愛」もそれだけではだめだということです。
センフにおける愛とは、「狂気」による中心から外への交通を肯定しますが、それと同時に、その力線の流入を中断する(否定する)ものでもあります。
外の世界が、最終的に自己同一性をそこなってしまわないように、「狂気」の流入を中断するということが、センフにおける愛なのだと思います。ライナ的なスタティックな愛と、「狂った愛」との間で、どちらか一方に偏らないようにバランスさせること。それによって、中心と外との恒常的な交流を可能にするということが、センフの目指した愛だったのだと思います。
センフの愛についてまとめ
●ライナ的な愛だけでは、個々の存在者は孤立してしまい、生存はしているが、「生きて」はいない状態に陥ってしまう。(外との交流がないと、存在は干からびてしまう。こうした観点からすると、サステナビリティとかは「生」ではないということになります。)
●「狂った愛」だけでは、例えば黙示録的イメージのように、最終的な世界の消滅という形でしか、「交流」がなされない。最後の一回としてしか「交流」がなされない。→センフにとっては、これは「愛」ではない。センフは常識的なところを持った人間だから。(諸存在の孤立は「悪」であるが、そうはいってもやはり、諸存在を侵害することは「悪」である。という立場。)
●「孤立すること」という「悪」(美徳、あるいは、愛や正義という名のもとにおいて行う悪)と、「存在を侵害すること」という「悪」(狂気・狂った愛)との間で、諸存在が孤立しているモーメントには侵害を行い(狂気の排出)、存在が侵害されているモーメントにはその力を中断すること(自身の排出)によって、どちらの「悪」も成就してしまわないようにバランスさせること。それがセンフの目指した「愛」なのだと思います。(世界をダイナミックな状態に保ち続ける。つまり、世界を「生きたもの」にしておくこと。最後の審判というのは、世界の「完成」であるかもしれませんが、ある視点からすると「世界の死」になると思います。)
センフは、「どこの世界、いつの時代に住む人びとをも愛さなくてはいけない。こんな非人間的な分野にたずさわっていればこそ、よけいそれに執着しなくてはならない。」と言っていますが、この「人びと」には、単に外の世界に暮らす人びとだけでなく、ライナも、気違い竜までも入っているということですね。
ライナと気違い竜の立場は対立していますが、センフは、自分を排出機にかけることによって、そのどちらをも愛そうとした(アウフヘーベンしようとした)のだと思います。(反・狂気としての「正常さ」がなければ、「狂気」は「愛」になりえない。同時に、「正常さ」だけでは、やっぱり「愛」は不可能である。ということ。)←これ、なかなかうまい言い回しだと思うんですけど、どうでしょう?(要するに、わたしがセンフを通して言いたいことは、世界を生きたものにしておくためには、みんながそれを生きたものとして「解釈」しつづけなければならない、ということのようです。書かれたもの(作品)は、なにをどうやっったって、それだけでは「スタティックなもの」にすぎません。誰かがそれを「ダイナミックなもの」として読まなかったならば、作品は死んだままであらざるをえないのです。というわけで、エリスンに対しては、あとのことは任せろと言ってやりたいと思います。)(言わずもがなのことですが、排出による狂気の流入とセンフによるその中断という繰り返しを、永遠回帰として解釈するということです。ここでいう永遠回帰は、エリアーデの「永遠回帰の神話」からですが、もちろん、ニーチェの永遠回帰と思ってもらってもかまいません。要するに、終末論的・黙示録的なイメージではなく、不断に生成されるコスモゴニーというイメージです。)
③ 愛は世界の中心から外へと向かうが、中心は誰から愛されるのか?
さて、crosswhenは「中心」ですから、時間の流れから超越しています。つまり、crosswhenで起こったかのように見える出来事(センフが排出法を開発したり、気違い竜を排出したり、センフが自身を排出したり、センフが死刑になったりといった出来事)は、実際には時間の流れのなかで起きた出来事ではなく、いうなれば世界創造(コスモゴニー)にほかなりません。(シジフォスやプロメテウスのように、竜とセンフは常に排出され続けており、センフの場合はさらに、ずっと死刑になり続けているといった感じでしょうか。)
ですから、外の世界とcrosswhenとの関係でいえば、常に、「中心から力・狂気・愛が流れ出している」ということになります。これによって、「外の世界」は「生きたもの」であり続けることができるわけです。
だが、もしそれを見出せば、彼らは知るはずだーー地獄が彼らとともにあることを、そして、天国と呼ばれるものが事実存在することを、そして、その天国の中には、そこからすべての狂気の流れ出す中心があることを。そして、ひとたびその中心へはいれば、そこに平和があることを。(p. 35)
ここでは、「外」の世界が、中心からアンビバレントな力をもらっているということが述べられており、それによって「外」の世界は人の生きる世界たりえていることがわかるわけですが、しかしながら、crosswhen自体は、いったいどこから力を得ているのでしょうか?
あるいは、「中心に入れば、そこには平和がある」と述べられているので、むしろcrosswhen自体は他からの侵入を受けていないスタティックな世界であるかのようでもあります。だとしたら、どうもわたしには少々問題があるように思えます。
それというのも、中心というのは、異次元への突破口であるからこそ「この世界」の中心たりえているわけで、言い換えると、中心が中心としての力を持つのは、そこにおいて異次元からの侵入があるからです。(参考、エリアーデ 『聖と俗』 pp.29-40 法政大学出版局)
その意味で、crosswhenから「狂気」の排出があるということは、「外」の世界にとっては、異次元からの聖なる侵入点になっているということであり、まさしくcrosswhenは世界の中心なのだといえるわけです。
通常の宗教学的解釈をする場合には、それゆえ、crosswhenは「中心」であるといって終わってしまって構いません。「外」の世界の人びとにとっては、crosswhenは「神々の世界」のようなものであり、そこがどこから力を得ているかは、必ずしも問題にしなければいけないわけではありません。(もちろんしてもかまいませんが。)この場合は、crosswhen(神々の世界)において、竜殺しによるコスモゴニーがあった、と語るだけで、創世神話としての体裁は整うと思います。
しかしながら、「世界の中心で愛を叫んだけもの」は、神話ではなくSFで、crosswhenは「外」の世界の人から見たら神々の世界に匹敵するかもしれませんが、その中ではセンフやライナといった人間が、彼らは外の世界の人間より次元が高い人間なのかもしれませんが、それでもやっぱり人間であるには違いない人たちが暮らしているわけです。crosswhenをこのような形で描写した以上、やっぱりcrosswhenにとっての中心は何なのかを問わなくては、フェアじゃないように思われるということです。
つまり、ちょっとよくわからないのは、
●「気違い竜」は、狂気の排出が完了したときに、「正常な人間」になった、と述べられていること。
●「そこ(中心)には平和がある」という点。
この二点です。
でもまあ、先ほどの引用部で、「天国の中には、そこからすべての狂気の流れ出す中心がある」と書かれているので、crosswhenの内部に依然として中心はあるとも読めますね。
そうだとすると、気違い竜が「狂気ジェネレーター」のようなものとしてcrosswhenの中心であり、さらにセンフが「狂気」を排出することによって、crosswhenが世界の中心にもなったわけだけど、ただし、依然として中心としての竜はcrosswhenの中にいるのだということになりますね。
これは、竜が人間に変化した(排出された残りは、正常で無害なものになった)と書かれていることとは矛盾するようですが、しかしながら、crosswhenは通常の時間経過を超越した場所であるので、まあそういうことも起こるんでしょう。あと、外から見たら、「龍が排出された時点」というのは、ある時点として特定できないわけですから、依然として竜がcrosswhenの内部にいるともいえるのでしょう。(排出は過去現在未来にわたる力動だから。つまり、狂気の排出について、センフは「完了した(終わった)」みたいなことを言っていましたけど、crosswhenの特質上、排出という行為は、過去現在未来のすべてにわたって現在進行形で行われていると考えるべきなのでしょう。だとしたら、竜も常にcrosswhenの中に居続けるということになるでしょう。)
というわけで、一点目はまあいいですけど、「中心」の内部が平和であり、「外」が「地獄」であるとされている点はちょっといまいちかなと思います。これってつまり、結局のところ「中心」と「外」との関係は、「加害」と「被害」の関係だということですよね。まあ、エリスンの考えではそうだったのだろうとは思いますが。(センフがライナに文句を言っているのは、ある程度本気で言っているのでしょう。)(わたしの解釈は、エリスンが考えていたのより、ちょっとセンフをかっこよく解釈してみたという感じではないかと思います。)
crosswhenの内部が「平和」であるというのは、ライナ的な意味で「狂気」の被害を受けていないということでしょうけれど、どうして被害を受けないのかというと、内部で発生した「狂気」をそのまま外部へ排出してしまっているからでしょう。というわけで、平和なcrosswhenというのは、わたしにはかなりしょぼいものに思われてなりません。いうなれば、中心である「気違い竜」と「外の世界」とをつなぐメディアに過ぎないというような感じですね。ジャイアンの威を借るスネ夫というか。
平和なcrosswhenは、エネルギーの源泉としての中心を内部にもっているようですけど、彼ら自身はそうしたエネルギーと直接交流することはなく、ただ単に、エネルギーを外へと排出する(伝達する)ための通路にすぎなくなっているように思います。その結果、自分たちは「平和」を、ライナ的な意味における「生存」を手に入れているようですが、そうした存在様態は、最終的には「生」の枯渇をもたらすのではないかと私はおもいます。
「世界の中心で愛を叫んだけもの」のラストは、シュツットガルト(西ドイツ)のとある廃墟の中で、男が七色の箱を見つけ、その箱を開けたところ、中から「つむじ風」と、「翼を持った、顔のない黒いものの群れ」が飛び出し、その翌日、第四次世界大戦が始まったというエピソードで終わります。
ここで、なぜ「第四次世界大戦」なのかというと、この小説は1968年に書かれたものなので、冷戦の真っ最中で、シュツットガルトにはアメリカ欧州軍の本部が置かれていて、要するに対ソ連の最前線だったわけですね。で、crosswhenはcrosswhenであって、アメリカのことではないわけですけど、もちろん、ある意味でアメリカを象徴してもいるわけです。それで、アメリカに対して「侵入」がありうるとしたら、まず真っ先に考えられるのが、ソ連による攻撃、すなわち世界大戦なわけですね。
つまり、9.11以降の世界では、アメリカへの「狂気」の流入がもっと手軽に可能になったので、「世界戦争」のような大規模破壊というようなあり方でなくとも、「中心」が「生」を取り戻すことが可能になっているかもしれませんけれど、冷戦当時には、どうやら「世界大戦」というイメージでしか、「中心」の活性化が想像できなかったのかもしれません。しかしながら、「世界大戦」という形での愛は、もちろん、「狂った愛」ですよね。「博士の異常な愛情」みたいな。(テロリズムも狂った愛であるには違いないんですけど、全面戦争よりは狂っていないと思います。)
もう一種類のアメリカへの「流入」のイメージは、ウィリアム・スタログですが、こちらの方は、ボーリングフォーコロンバイン的にもうとっくに現実になっていますね。これは日本でも起きていることですけど。
で、結論として少々教訓的なことを言うとすると、あんまりライナ的に閉じこもっていると、「狂った愛」が爆発してけものが叫んじゃうかもよ、ということでしょうか。
あと、最後にわりとどうでもいいことですが、「ビースト」を「けもの」と訳すのは、この話では基本的に竜的なもののことを言っているので、日本語で「けもの」というと「毛のある動物」という意味になってしまって、ちょっとわたしとしてはイメージと違うので、あんまりよろしくないんじゃないかなと思いました。
あと、さらにどうでもいいことですが、「世界の中心で愛を叫んだけもの」って、けものを平仮名で書いているので、「世界の中心で愛を叫んだっけもの」って読んでしまいますね。わたしの地元の庄内弁ですが。「叫んだっけ(過去形)」+「もの」で、「世界の中心で愛を叫んだのだったもの」っていう意味になって紛らわしいです。
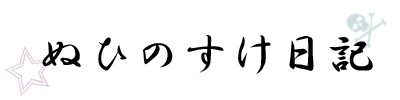
長文お疲れ様です。
参考にさせていただきます。
気になった点
・歌麿師匠?歌丸師匠?
・永遠回帰?永劫回帰?
今さらですがコメントどうもです。
歌丸師匠はその通りですね。間違いでした。
永遠回帰については、英語だとeternal returnです。ニーチェの術語だと永劫回帰と訳すことが多いですが、ここで言ってるのは直接的にはニーチェではなくて、宗教学者のミルチア・エリアーデで、”The Myth Of The Eternal Return”という本があるのですが、これの訳は『永遠回帰の神話』となっているので、永遠回帰と言っています。宗教学における永遠回帰には、別にニヒリスティックな意味はありません。むしろそれ以外には実在などないのだという感じですね。