今日はちょっと、わけのわからないことを言おうと思います。
考えを述べる際のスピードを5段ギアだとすると、最初の方は3速くらいですが、後半は4速ギアくらいで書いている感じなので、まあわたしと似た考え方をする人以外は、ほとんどなにを問題にしているかわからないだろうなという自覚はあります。(ちなみに5速で書くと、後から自分で読んでも理解できないことが多いです。そうやって書くことは楽しくないわけではないので、昔はよくやっていましたが、最近は年をとって体力がなくなったからか、あんまりそういうことはしていません。)
とはいえ、ここはわたしのブログなので、たまには好きなように書いてもいいだろうということで、ちょっと書きたいことがあるので書こうと思います。どっちにしろ見ている人はほとんどいないわけだし。
『見えない宗教』についての雑談
一去年亡くなったトーマス・ルックマンという人の書いた「見えない宗教」という本があって、わたしは大学1年のときに宗教学の授業で読まされたんですけど、さっきちょっと見ることがあったので、10分ほど斜め読みしてみたんですが(こういう本を一冊読むだけの根気が最近はなかなかわきませんね。1パラグラフで要約してほしいと思ってしまうw自分のことは棚に上げて。)、全体的な話としては、近代になって社会が多様化し、人々が専門化することによって、社会全体が究極的に根拠づけられるような共通の聖なるキャノピー(信憑構造)は存在しえなくなった。その代わり、パッケージされた諸価値を個々人が選択して、自分だけのキャノピーを作る(消費する)ようになったのだというような話でして(10分読みなので間違ってるかもしれません。ちゃんと知りたい人は自分で読んでください)、そういう個人化した宗教をインビジブル・レリジョンといっているわけなのですけど、これはまあ『プロ倫』の進化版というか、宗教の内容ではなくて、形態それ自体が新しい形に変化してるという意味で、なにやら根本的に新しい時代が来たのだというようなことを言っていて、その気負った感じというか盛り上がった感じが、かなりキリスト教っぽいというか、終末論ぽい感じですねと思いました。(どこからかThe final count downが聞こえてきそうな感じ。)
この本は1960年代の本で、ベラーとかよりちょっと前ですけど、だいたい同じころで、つまりはまあ、そういう時代だったんでしょうねえ。(ヒッピーとか禅ブームとかドラッグとかサイケの時代ってことです。)
今から見ると、こういう個人主義って、経済成長だかパックスアメリカーナだか神の見えざる手的な資本主義だか知りませんけど、そういう世俗的ではありますが十分共有されてる聖なるキャノピーに守られた範囲において、ちょっと反抗してみたという程度の話なんじゃないかと思います。(実際には信憑構造によって守られていたからこそ、「共通の信憑構造がなくなってしまったぜ!」というストーリーを楽しむことができたというか。)
ルックマンにせよベラーにせよバリッジにせよ、彼らのまわりには確かにそういう「個人主義」的な人が実際にいたんでしょうけど、どうも世の中そんなにインテリばっかりじゃないというか、昨今のポピュリズムやファンダメンタリズムの流行を見ると、言われてたほど「個人主義」な世界になってたわけじゃなかったんだろうなと思います。
つまり、経済的なことが原因なのか、政治的なことが原因なのかはわかりませんが、「共通の信憑構造がなくなってしまった」というようなストーリーを楽しむ余裕がなくなったときには、なりふり構わず、全体主義的だろうとなんだろうと、とにかく社会全体を根拠づけるような「共通の」信憑構造を取り戻そうとする人々が一定数いる(思っていたよりもかなりたくさんいる)ってことなんじゃないかと思います。
インビジブルとビジブル
ルックマンのいうインビジブルというのは、表面的には個人化のことですが、根本的にはキリスト教が非制度的宗教だったというときに言われているような内面化のことを指しているんだと思います。つまり、見えるものに対しての見えないものこそが重要だと考える態度から帰結する結果だということですね。で、宗教的には、見えるものが見えているとき、本来であれば、それと同時に、見えないものが見えるものとして見えているという次元があると思うんですけど(それをまあ、神秘といってもいいです。わたしとしてはヒエロファニーといいたいです。)、見えるものを単なる見えるものに還元してしまって、そのうえで「見えるものじゃなく、見えないものこそが重要なのだ」といっているような感じで、わたしからすると、ちょっと前提が間違っているんじゃないかと思わないでもないです。(これはわたしが、解釈の基本的枠組みを、いわゆるアルカイックな宗教に負っているからそう思うわけです。)
つまり、インビジブルという視点を導入することによって、本来ビジブルかつインビジブルなものとして体験されていたことが、心身二元論的に分離してしまうというような感じで、もともと可能であった体験がいったん不可能になった人にとって、もともとの体験を「取り戻す」ためには必要な行為であったのでしょうけど、もともとの体験が未だ失われていない人にとっては、ある意味余計なお世話でないわけでもないということです。
中国における禅宗なんか、多分にその気があったんじゃないかと思います。つまり、見えるものに対して見えないものこそが重要なのだというのは、確かにある種の批判力があるわけで(星の王子さまとか)、それが最初に発見されたときにはたいへんラディカルな威力を発揮するわけですけど、インビジブルなものをインビジブルという言葉によって可視化してしまうので、結局のところインビジブルなものをビジブルなものに還元しているには違いないんですよね。(体験において、インビジブルなもののビジブル化が最終的なものではないということが担保されていればいいんですけど、単に言葉の上だけでの話になってしまうと、簡単に野狐禅になってしまうということですね。だから禅のお師匠さんたちは、弟子を殴ったり、指を切ったりということをやるわけですけど、そういう行為もまた、ひとつの型として理解することは可能なわけで、指を切られたお弟子さんは、だからこそ指を切られちゃったわけですけど、つまりは簡単に「堕落」しやすいということです。cf.倶胝竪指)(デコンストラクションなどというのも、同じ仕組みのものだと思います。容易に「堕落」しやすいという点も含めて。)
で、ルックマンがいうように、最初は「非制度的」宗教だったものが、「非制度的」とされる制度的な宗教になって、「非世俗的権力」(非権力的権力というか)をもって、そんなのは嘘といえば嘘なわけですから、それに対してプロテスタンティズム的な否定作用が起きて、それによってインビジブルなもののinvisibilityが回復されるという仕組みなんでしょう。
で、最終的には、世俗化という形で、「非宗教化」することによって逆説的に宗教的なものに接近しようとするわけなのでしょうから、ルックマンの言うことも、キリスト教関係についてはそうなんだろうと思いますけど、これはまあ、サクリファイスの構造と同じことで、さすがにキリスト教というのはイエスをサクリファイスしたというのが根本的な宗教体験であるような宗教なので、最終的にはそういうことになるのかもしれないというのはわかる話ですけど、世界中の人がそんな手の込んだことをしてると思うなよ、と、わたしなんかは思うわけです。
まあ、それはそれでドラマチックなことで、そういうことをするのは楽しいことだろうからご自由にどうぞと思いますけど、だからといって、そんなふうな手の込んだやり方を使わない人に対して、程度が低いだとか、本質的なことがわかっていないだの、宗教以前だなどといったりするのは、ちょっとイラっとしないでもないです。
還元することで、はっきり「理解」することができるけれど、同時にビジブルなものに「限定」してしまう。無限定だったときと比べると「意味」が減る。しかしながら、何もしなかったのなら、実は何もなかったのだから、どんな限定であれ、とにかく限定するということは必要なことだったのだし、「必要なことだった」というよりもむしろ、その限定の瞬間(創造の瞬間)には、それは絶対的に「完璧」なものであったのだ。そういう最初の「限定」(創造の瞬間)を肯定しようとすることは、わたしにとってはかなり重要なことです。(cf.香厳上樹)※1
「神さまなどいない」という人はまあまあいるけれど、その人たちが「本当に」(というのはその人の存在全体においてという意味だけれど)「神さまなどいない」と思っているわけではないと思います。(特に日本においては。)例えばわたしは、去年村の神社の修復費用に6万円払ったのだけれど、「いない」もののためにお金を払う人はいないから、何らかの意味では「いる」と思っているわけですね。6万円は払わないにしても、50円とか5円とかならお賽銭をあげたりもするわけで、ほとんどの人は、その程度には「いる」と思っているわけです。また、そもそも神社で頭を下げたりもするわけで、「いない」ものに対してはなにもすることはできない(だって本当に「いない」もののことは対象にできない)わけだから、そういうことをする以上、何らかの意味で「いる」と思っているのは間違いありません。(「いないもの」として「いる」とか。)
もっとラディカルに、神さまなんていないから、わたしはそんなことはしないとかいうこともできるけど、そういったとて同じことで、本当に「いない」ものについてはどんな言明もできないのだから、「いない」という述語を付けることすらできないわけです。
つまり、一度「ある」という状態になったもの(創造されたもの・誕生したもの)は、もうどうやったって「ある」ことからは逃れられないんですね。これをコスモゴニー(世界創造)という。コスモゴニー(創造)は不可逆な出来事です。
(創造(インビジブルなもの)それ自体が重要であるが、創造は被造物(ビジブルなもの)の創造としてしかありえないので、あたかも被造物(ビジブルなもの)こそが創造の目的であったかのような様相を呈することはままありますが、創造に先立って被造物が存在するわけはありませんので、そういうレトリックは実は嘘です。)
体験として全体的に把握していたことを、概念的に(インビジブルなものというビジブルなものとして)表現してしまってよいのだろうかということ。(これはわたしが個人的に悩んでいたこと。)
解釈というのは、無・限定だったものを限定することです。だから、解釈によって生まれたもの(内容)は、解釈されたものよりもある意味で常に劣っている。しかしながら、限定する前には無・限定、つまり無だったのだから、その意味では、そもそも有にならなければ何事も始まらないわけです。(優劣は有と有との間でしか比べられない。)
つまりどんな解釈であっても、解釈しないよりは解釈した方が断然いい。(解釈というのはほとんど理解と同じ意味です。)
しかしながら、言語による解釈以前の解釈(了解)が体験としてあるならば、わざわざ言語的に解釈することはあまり良いことではない場合もあると思う。(これは15年ほど前にわりと本気で思っていたこと。)
もともとは「ビジブル=インビジブルな体験」(要するに普通のシンプルなヒエロファニー)が可能だった社会において、「大事なのはインビジブルであってビジブルではない」と誰かが言った場合(偶像崇拝はいかんとかそういうのですね)、たしかにインビジブルをそのものとして把握することが可能になるし、インビジブルな体験の相はそのように言うことによって、より明確に(純粋に)体験できるようになるわけだけれど、それは一方で、インビジブルを「インビジブル」という名のビジブルに還元してしまうことでもあるわけなので、そのような迂路を通らずに「ビジブル=インビジブルな体験」が可能だった人にとっては、楽園追放にならないとも限らない、というわけですね。智恵の実を食べさせる蛇の役割というか。もちろん、蛇は蛇なりに、良かれと思ってやっているわけではあるのですけれど。
単なる永遠回帰から、意味の(解釈の)永遠回帰へ
というわけで、ルックマンの議論については、いろいろ文句もあるわけですが※2、しかしながら、わたし自身について言えば、ルックマンの議論はだいたい当たっているんだろうなと思います。わたしは宗教学をやっていたわけですけど、わたし自身が他者の宗教体験を解釈しようとするのは、わたし自身にとってのインビジブル・レリジョンを構築するためだろうからです。なんだかんだ言って、わたしも現代人には違いないということですね。
例えば神話解釈の場合、神話というのはそれが生きたものであるときには、それ自体が「世界の意味」であって、いうなれば神話自体が問いに対する「解答」なのだから、それ自体の意味(神話の意味)を問わなければならないようなものではありません。「神話の意味」を問わなければならないという時点で、
神話(ビジブルなもの)⇔ 神話の意味(インビジブルなもの)
という分裂がおきてしまっているということです。
もっとも、神話は「記述」されるようになった時点でそういうものになってしまっている場合がほとんどです。日本の場合でいえば古事記が編纂されたころには、既にある程度そうなってしまっていたでしょう。これは、ソクラテスが文字を信用してなかったというのと似たような話だと思います。(「あなたの言われるのは、ものを知っている人が語る、生命を持ち、魂をもった言葉のことですね。書かれた言葉は、これの影であると言ってしかるべきなのでしょうが。」パイドロス276A)
わたし自身にとっては、神話はそれ自体として体験されるものというよりは、やはり「意味」を問われなければならないものであるので(日本神話について言えば、普通の人よりはそれ自体として体験できると思いますけども、そうはいってもやはり)、わたしの解釈はわたし個人にとってのインディビジュアルで他の人にはインビジブルなレリジョンになっているのでしょう。
というわけで、わたしはわたしの行った解釈(の内容)を、「共通のキャノピーですよ」と言って他の人に示すことはできません。(で、こうなってくると、なかなか「学問」の体裁を保っているのが難しくなってくるのですが。)
それはさておき、「ビジブル=インビジブル」の体験(アルカイックなヒエロファニー)と、「ビジブル≠インビジブル」の体験(もうちょっと「高級」な宗教体験)を比べると、次のように言えるかと思います。
アルカイックなヒエロファニー
「ビジブル=インビジブル」の体験といっても、常に必ずビジブルなものがインビジブルなものであるわけではなくて、そういう時と場所においてのみ、そういう体験が可能になります。(分析的にいうとこうなりますが、当然ながら実際は、そういう時・そういう場所・そういう体験は一つのことであって分節されていません。)
で、ビジブルなものの本質は、インビジブルなものがビジブルなものになったというところにあります(創造の瞬間における被造物)。ただ、そうした還元は一瞬のことで、インビジブルなものがビジブルなもののうちにずっと顕現し続けているわけではありません。(そういう意味では、「象徴」というのはけっこうヤバいものですよね。いいものではあるんですけど。「象徴」がさらに進むと、「概念」とか「意味」になるんだと思います。※3)
一般的にいえば「儀礼」とか「祭り」とかの場合ですね。そういう時、インビジブルなものがビジブルなもののうちに顕現しますが、儀礼や祭りが終わってしまえば、ビジブルなものは単なるビジブルなものに戻り、インビジブルなものは消えてしまいます(インビジブルなものが「消える」って、何のことやらとは思いますが)。ただ、ビジブルなものが一瞬でもインビジブルなものとなったという事実は消えないので、つまり、ビジブルなものの本質はインビジブルなものの自己限定であるという事実は消えません。そういう形でインビジブルなものはビジブルな世界を聖化(サクリファイス)しているということですね。で、同時にそれは自身を犠牲(サクリファイス)にしているということでもあるわけです。
かつまた、インビジブルなもの自身についても、儀礼や祭りの時が終われば、ビジブルなものの中から出て行ってしまうので、インビジブルなものをビジブルなものとして固定(還元)してしまう危険はあまりありません。(さっきも言ったように、「象徴」の場合は微妙ですが。)
というわけで、ビジブル=インビジブルの体験は永遠回帰的です。「常にずっと」ということはありませんが、「そういう体験」は定期的に可能なのです。
インビジブルなものをビジブルなものに還元してしまう危険を回避するために、祭りにおいてインビジブルなものの入れ物になったビジブルなものを破壊してしまうという場合もあります。サクリファイスはだいたいそういうことです。キリスト教風に言えば、神の物は神に返すべきなのです。キリストの磔刑。あるいはイオマンテとか。もっと簡単に、神さまの乗っていない神輿はただの神輿である、ということでももちろんいいんですけど。
ビジブル≠インビジブルの体験
これに対して、ビジブル≠インビジブルの体験では、インビジブルなものが「非―意味」という意味として、それ自体一つのビジブルなものとして固定(還元)されてしまいます。インビジブルなものが概念(意味)として把握されるので、そういう「もの(ただし抽象的な「もの」)」として還元されてしまうということです。確かにそうすることによって、インビジブルなものの顕現が、「常にずっと」可能になるわけではあるのですけれど、そうはいっても、それはやはり「還元」には違いないのです。(リクールだと、インビジブルなものについては「宣言」と言っていて、顕現と区別していますね。わたしはビジブルなものの立場からインビジブルなものの顕現をみるので、どちらも顕現といっています。)
永遠回帰の場合は、一度のヒエロファニーには「終わり」があるので、次にヒエロファニーがあるときには、また最初からやりなおせばいいだけのことです。それに対して、インビジブルなものが「常にずっと」顕現している場合、新しいヒエロファニーが起こるためには、その媒介となった「俗なるもの(概念)」を廃棄しなければならない場合があるのだと思います。
永遠回帰の場合は、メディアとなった俗なるものは、祭りが終われば常に「俗なるもの」へと戻るので、インビジブルなものの都合によって、いわばいちいち「廃棄されている」ともいえます。で、そのおかげで、インビジブルなものはインビジブルなもののままであることが可能(正確には「インビジブルなままであることが可能」なわけではなくて「ビジブルでないものになる=なくなる」だけですけど)なのです。(つまり、知的に把握しないことによって、「神秘的」なままにしておくことができるということ。)それに対して、インビジブルなものを概念的なビジブルなものへと還元してしまう場合、そうした概念そのものを廃棄しなければ、次なるヒエロファニーが可能にならない場合があるということです。
もっとも、概念の廃棄といっても、そうしょっちゅうしなければならないわけではなくて、井筒俊彦の「コスモスとアンチコスモス」でいわれていたような感じで、コスモスの信憑構造が機能しなくなった際に、そういう抜本的なヒエロファニーが必要とされるということなんでしょう。カソリックに対するプロテスタントのように。大々的なリニューアルが必要になるときの話なんだと思います。(この辺のことについては、いろいろ言いたいことがありますけど、今回はやめておきます。)
最近わたしはこんなふうに考えている。
さて、わたしが宗教現象を解釈する場合、わたしはある宗教現象から「意味」を取り出すわけですけど、この「意味」というのは、わたしにとっては、インビジブルなものが「インビジブルなもの」という名のビジブルなものとして現れた形です。ですから、その顕現が一つのヒエロファニーであるには違いありません。しかしながら、わたしが文としてそれを書いた場合、それはどうしたってそういう形にインビジブルなものを還元してしまうことであるわけです。で、インビジブルなものをビジブルなものに還元してしまうということは、インビジブルなもののinvisibilityを否定することに他なりません。
しかしながら、よく考えると、わたしの書いた文は、わたしがそれを書いているときとか、わたしやほかの人がそれを読んでいるときには、ある「意味」を媒介にしたヒエロファニーになりえますけど、読まれていないときには「存在していない」ものです。(文は書かれているときとか読まれているときには「存在」していますが、誰にも読まれていないときには「存在」していません。この場合の「存在している」というのは、「誰かの体験においてリアルに存在している」という意味です。そうした形態での「存在」というのは、永遠回帰的なものなのだと思います。)
文とか考えというのは、少なくともわたしの場合は、絵というよりは音楽に似ているものなので、それが誰かの体験においてドライブしているときには「存在」している、つまり、インビジブルなものがビジブルなものにおいて顕現しているわけですけど、読み終わってそれについて考えなくなれば、単なる文字の羅列とか紙の束とかネット上のデータとかに還元されてしまいます。さすがにその中にインビジブルなものが「ものとして」存在していると思う人はいないでしょう。
というわけで、最近わたしは、文にすることによってインビジブルなものをビジブルなものにしたとしても、少なくともわたし自身に限って言えば、別に気に病むほどのことではないなと思っています。というのも、そもそもわたしの文を読む人はほとんどいないし、いたとしてもそれを「教義」とかみたいに「正しいこと」と思う人なんているわけがないので、わたし自身がそう思わなかったなら、別に何の問題もないなと思うからです。
わたしが職業としての「宗教学者」とかになっていて、なんか学問として権威あるものを書いているとかいうのだったら問題になることもあるでしょうけど、幸か不幸かそういうポジションにはついていないので、こうやって個人のブログに気楽に書いている分には、そんなに罰当たりなことをしているわけでもないだろうと思うわけです。
※1
「人の樹に上るが如し。口に樹枝を啣み、手に枝を攀じず、脚樹を踏まず、樹下に人あつて西来意を問はば、對へずんば即ち他の所問に違く、若し對へなば、また、喪身失命せん。まさに恁麼(いんも)の時、作麼生(そもさん)か對へん。」『無門関』第五則
ちょっと説明します。「言葉(概念・意味)」におけるヒエロファニーというものを考えたとき、発声された言葉ならば、言葉として聞こえる「音」によって「意味」が創造されますが、発声された「音」が消えることによって、その「意味」もとりあえずは消えます。「意味」がリアルである体験が終わるということですが。言葉のリアリティーとは本来はそういうもので、また、そうであるからこそ、言葉は「ヒエロファニー」たりえるともいえるわけです。(ずっと持続するものは「俗なるもの」ですから。)
ですから、この話の場合は、「祖師西来意」という「意」も、木の枝に口でぶら下がっている状態から、口を開いて「発声」して、口を開いたから木から落ちて、下に落ちて死ぬまでの間であれば、それがどんな「意」であっても「聖なるもの」たりえている、という意味です。
別に発話した人が木から落ちて死ななくてもかまわないんですが、ここで死ぬといっているのは、むしろ発話された「言葉」の方なんですね。ヒエロファニーとしての言葉が、正しくヒエロファニーであるのは、人が木から落ちて死ぬまでの間、その声が響いている間くらいのものだということです。(「真実」とか「真実在」というものは、そういう形でしか到達(体験)できない、という意味です。そしてもちろん、人間によって体験されない意味は、存在しません。意味は人間の体験においてのみ存在しうるものだからです。)
言葉が文字に記され、あたかも「意味」がずっと持続するかのようであっても、その言葉(概念・意味)は持続するものとしての言葉であって、「俗なるもの」としての言葉です。
「意味が意味する」とか「言葉が意味する」というその意味作用は瞬間的なものです。そういう瞬間に言葉は「聖なるもの」となりますが、それは「意味が意味する作用」が生きている間だけで、意味作用が終了すると、言葉(概念・意味)はたんなる言葉(概念・意味)に還元されます。つまりヒエロファニーが終了したということです。
例えば詩が一つの意味作用のために一つのセンテンスであらねばならないとき、できるだけ短くなければならないのは、言葉は発話された(意味を生成した)端から、単なる言葉へと帰っていく(死んでいく)からです。詩人は、言葉が死ぬ前に言うべきことを言っておかなければならないので、急がざるをえないということです。
このように、「言葉(概念・意味)」は、それが意味生成的であるとき(そのようなものとして体験されているとき)はヒエロファニーですが、それ以外の場合は単なる俗なるものとしての言葉です。とはいえ、意味生成的に発生したものだという事実は消えませんから、「俗なるもの」としての言葉は、常にヒエロファニーたりえるものでもあります。しかしながらこれは、「聖なるもの」が「常にある」という意味ではなく、常に再生(復活)する可能性のある「俗なるもの」だということで、これは一般的なヒエロファニーにおける「俗なるもの」と同じ仕組みです。(ヒエロファニーの再生(復活)のしやすさという利点があることは間違いないですが、その分、誤解する余地も大きい媒体だと思います。「誤解」というのは主に「文字」についてですが。)
※2
ルックマンの議論に文句があるといっても、ルックマン自身に文句があるのではなく、ルックマンが参照している宗教現象の態度(聖なるものに対しての態度)に文句があるということです。宗教学では「クラシカル」な態度といいます。キリスト教やイスラム教や仏教などの態度です。(『宗教学入門』1962、J.M.キタガワ 編M.エリアーデ 編岸本 英夫 監訳、東京大学出版会に、キタガワの書いた「クラシカル」の説明があります。)
※3
Mircea Eliade, 1958, “Patterns in Comparative Religion” Trans. by Rosemary Sheed, University of Nebraska Press. p.447
“Futher, while a hierophany presupposes a break in religious experience (for there always exists, in one form or another, a breach between the sacred and the profane and a passage from one to the other — which breach and passage constitute the very essence of religious life), symbolism effects a permanent solidarity between man and the sacred (though this is somewhat indistinct in that man only becomes conscious of it from time to time). A talisman, or jade, or pearls, permanently project anyone wearing them into the sacred zone represented (that is, symbolized) by the ornament in question; and this permanence can only not be effected by means of a magico-religious experience which presupposes a breach between profane and sacred.”
(赤字部分、notであるべきところonlyとなっていて、たぶん誤植です。仏版確認済み。この本誤植っぽいのが多いんですよ。)
「ヒエロファニーは、宗教体験における裂け目を前提にしている(というのも、聖と俗の間には常に何らかの形で「断絶」と「移行」があり、しかも、そのような断絶と移行こそが宗教的生の本質をなしているから)のに対して、シンボリズムは、人間と聖なるものとの間に、恒久的なつながりを実現する。(もっとも、そうしたつながりについて、人間はたまにしか自覚的にならないので、いささかあいまいなものにとどまってはいるのだけれど。)護符、翡翠、真珠などは、それを身につけている人を、いつも必ず、それらのものがあらわしている(つまり象徴している)聖なるゾーンへと投げ入れるのだが、この「いつも必ず」という性質こそは、聖と俗の断絶を前提とする魔術・宗教的体験からは導かれないものなのである。」
→「いささかあいまいなものにとどまっている」というところ、含蓄がありますね。
宗教体験(体験一般といってもいいですが)にとって、「明晰に理解する」ということは、一概によいとばかりは言えないと思います。
オットーは、非合理性の体験が合理的な言葉や概念(言葉や概念はそもそも合理的なものなんですが)によって図式化(合理化とは違います)されているという点に、キリスト教が他の宗教よりも優れている点を見るわけですが、たしかに「反対の一致」的には優れていると言えなくもないとは思いますが、やっぱりわたしは一概に「優れている」とは言えないと思います。
単にキリスト教というか「クラシカルな宗教」が、そのような形態のヒエロファニーを好んだというか、「クラシカルな宗教」が発生するには、それ相応の実存状況(歴史的状況)があり、そうした実存状況に対応したヒエロファニーが「発見される」のであって、つまり、別の形態のヒエロファニーとの違いは、もとになっている実存状況の違いであって、ヒエロファニー自体に価値的な上下があるわけではないと思います。
人々の生活が一様でなくなり、なんらかの点で「抽象化」しないと、「共通の世界」を持つことが出来なくなり、それゆえ、言葉とか概念といったものを媒介とした「抽象的な」ヒエロファニー(意味におけるヒエロファニー)という様態が現れたのではないか、ということです。
それを「進歩」ということもできるでしょうが、それをいうなら、「堕落」ということだってできると思います。つまり、どちらのタイプの宗教体験を基準にするかというだけのことだと思います。
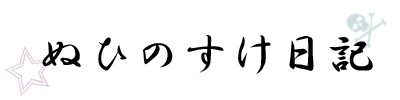
8p9eeh