昨日テレビで『もののけ姫』をやってたので、もう何回目かわかりませんけど、また見てしまいました。
皆さんそうだと思いますけど、何回も見ているので、セリフとか動きとか、ほぼすべて覚えてしまっています。すごく好きというわけでもないんですけどね。
最初にもののけ姫を見たのは公開時ですから97年ですか。もう20年にもなるんですか。
わたしは、だいぶ前につぶれてしまった西武の6階の映画館で観ました。
修論を書いた翌年で、修論では風土記に出てくるタタリの話をやってたので、タタリ神的に楽しみにしてたんですけど、タタリ神的にはいまいちな話でがっかりでした。
昔書いたたたりの話
修論の時、副指導をしていただいた先生と、先生の息子(中学生)と、同じゼミの数名とで、わいわい見に行ったんですが、先生はちょうどそのころ互酬性の倫理的な話をやってらした(ちょっとはやってた)ので、人間と森の神さまとの互酬的世界みたいに解釈されていて、つまりタタリというのはそういう互酬性が取り戻される出来事というわけで、「ぼくはなかなか良かったと思うよ」とかおっしゃっていて、まあ、宮崎駿の考えてることはだいたいそういうような感じだろうから、素直な解釈ではあるんでしょうけど、わたしとしてはやっぱりタタリ神がしょぼくてがっかりでした。
タタリ神
タタリ神的にがっかりしたといっても、グラフィックのことではなくて、ストーリー的な描かれ方の問題です。
グラフィック的な描かれ方としては、最初のナゴノカミ登場シーンは、タタリ神的にかなり良かったというか、あとのダイダラボッチのシーンより断然かっこよかったですね。
ただ、最初が良かっただけに、タタリ神については出オチ感がかなりありましたね。
もののけ姫におけるタタリ神というのは、姫が「タタリ神になんかならないで」と言ったり、オッコトヌシが「一族からタタリ神を出してしまうとは」とか言ってるので、もともとそういう神さまであるわけではないものが、何らかの事情によって「なる」(変身する)ものであるようですね。
で、タタリ神になる(変身する)といっても、ナゴノカミにせよオッコトヌシにせよ、あの黒紫のうねうねドロドロは、彼らが生やそうと思って生やしているわけではなく、自然に生えてきてしまうもので、しかも、あれが生えると、それなりに熱かったり苦しかったりするようです。生えるから苦しいのか、苦しさから生えるのかはわかりませんが、とにかく、本人たち(イノシシですが)にしても、タタリ神になりたくてなっているわけではないようですから、彼らは実はタタリの主体ではなくて、むしろ祟られている側というべきですよね。
つまり、最初に登場したタタリ神は、ナゴノカミの身体をもとにしたタタリ神として暴れていて、タタリ神が暴れるとアシタカをはじめ周りの人たちは困りますけど、一番困っているのはむしろ自分の身体を乗っ取られてしまったナゴノカミなんだと言えなくもないだろうということです。
劇中では、ナゴノカミがタタリ神になったと言われており、これはまあ、間違いではないわけですけど、むしろナゴノカミは祟られた側で、タタリ神に憑かれた(ポゼストされた)という方が正しいように思います。(で、ナゴノカミに祟ったタタリ神の正体は不明ということ。実際のところ、名前はまだない神なんだろうと思います。森光子がこれからお祭りしていくらしいので、今から名前が付くのでしょう。メディアになった「ナゴノカミ」の名前をそのまま付けてしまうのかもしれませんが。)
たとえば沖縄ではカミダーリという現象があって、これは何らかのものに祟られて具合が悪くなることですが、祟られた人は、それをきっかけにお師匠さんについて修行して、ユタなどの神人(かみんちゅ)になるわけです。(今ではならない人もいますけど。その場合は、病院に行って統合失調症等の診断をうけて治療するようです。)
ナゴノカミやオッコトヌシにおけるタタリもこれと同じような感じで、だから正確には、彼ら自身が「タタリ神になった」というより、よくわからない「タタリ神」が彼らを通じてこの世に現れた(ヒエロファニー)のだ、というべきだと思います。
うらみとタタリ
もっとも、もののけ姫におけるタタリ神には、「不慮の死を遂げた人がタタリをする」という考えの影響もあるようで、その考えでいくと、ナゴノカミはエボシに鉄砲で撃たれて死んだから、その死の異常性とか恨みとかによってタタリ神になってしまったのだという説になります。(ナゴノカミは、「けがらわしい人間どもよ。わが苦しみと憎しみを知るがいい」と言っています。)
こうした考えは、文献的には例えば三代実録の貞観五年(863)五月廿日の記事の記述が有名ですが、長屋王の変(729)以降、政権まわりではわりとポピュラーな考えであったように思われます。三代実録では、御霊の説明として、
所謂御靈者、崇道天皇、伊豫親王、藤原夫人及觀察使、橘逸勢、文屋宮田麻呂等是也、並坐事被誅、寃魂成厲、近代以來、疫病繁發、死亡甚衆、天下以爲、此災御靈所生也、
いわゆる御霊は、崇道天皇、伊予親王、藤原夫人及び観察使、橘逸勢、文屋宮田麻呂などのことである。事件に連座して誅せられ、無実の罪で死んだ人の魂が疫病を引き起こすのである。近頃、疫病が多発して死ぬ人甚だ多く、天下の人みな、この災いは御霊が生まれたからだと思った。
と書かれているのですが、この説明は、死んだ人を生きた人と同じようなものとみなしていて、宗教的におもしろいものではないですね。(結局のところ、生きている人間同士のドラマとして処理されてしまっていて、つまらないということ。)
政争の当事者だった人たちにはリアルな話だったんでしょうけど、単に、倒された人の幽霊かなんかによる仕返しを恐れているだけのことで、倒した人によるうしろめたさなのか、あるいは「民衆による政権批判」というような解釈もありますけど、そういうことなのか、要するに、単にこの世の出来事をこの世的に解釈しているだけなので、あまり宗教的とはいえないわけです。
もっとも、「すでに死んでいる人によって殺される」というのは、よく考えてみると、「生きている」とか「死んでいる」とかいう区別が攪乱される体験にもなるわけなので、まったく宗教的でないというわけではないんですけどね。(能における幽霊なんかはこうした感じですね。あるいは、シェークスピアにおける幽霊とか。)
また、「民衆による政権批判」的な解釈の視点からいうと、政治がやっていること(この世的なこと)全体が、あの世的なものによって価値転換されるという構造があるともいえるので、民衆にとってのタタリ神になった偉い人(長屋王とか道真とか平将門とか)というのは、宗教的な意味でちゃんとした神さまだといってよいと思います。(この場合は、政争で死んだ人が、自分の政敵だった人やその一族に対して仕返しをするだけではなく、関係ない人をたくさん殺す疫病を起こしたりする、というところが「神的」なのだと思います。)
しかしながら、ナゴノカミがエボシに鉄砲で撃たれて、それを恨んでタタリ神になって云々という話だとすると、エボシがいうように、「馬鹿なイノシシめ、恨むなら私を恨めばよいものを」という話になるほかはないわけですが、先に述べたように、タタリの実態は、ナゴノカミ自身に由来するものではなく、ナゴノカミに憑りついた、名前はまだない何者かの仕業なので、ナゴノカミの感じていた恨みの心は、そういうものが憑りつくきっかけにはなったかもしれませんが、タタリ自体の根本的な原因ではないと思います。
シシ神
つまりわたしが言いたいのは、神さまというのは「よくわからないもの」でなければならないということです。(そうでなければ神的ではないから。)
「恨み」というのは非常に合理的なもので、「恨んだから仕返しをした」というのは、説明としてはわかりやすい話ですが、それだけに、そういう説明によって説明されてしまうものは神的とはいいがたいものだと思います。(ギリシャ悲劇で、デルフォイの神託とかで、ある予言をもらって、それを避けようと行動したところ、まさにその回避行動によって予言が成就してしまうとか、そういう理不尽さがないと、「神的」とはいえないということです。その意味では、オリンポス神群はそれほど神的ではないともいえるかと思います。これは日本のアマテラスとかスサノヲとかが、神話の主人公として活動している間はそれほど神的ではないというのと同じです。岩戸神話におけるアマテラスなどは、神というより神をまつる人ですよねという話です。あるいは、黄泉国におけるイザナミは神的ですが、イザナキは神的ではないということです。神的なものというのは客体的なものということで、主体的なものではないということなんでしょう。つまり、主体性こそが人間性で、神性というのはそういう主体に対して客体的に現れるものだということでしょう。)
その意味で、もののけ姫におけるシシ神は、実に神さまらしい神さまだと思います。まったくしゃべらないところが良いですね。(前提として、例えばシシ神が一歩歩くたびに、地面から植物がぶわっと生えて枯れるところとか、そういう圧倒的な力の働きがあって、しかもそうした力が「よくわからない」ものであるから神的なのですが。)
モロやらオッコトヌシやらは、よくしゃべるので何を考えているかわかってしまいますし、しかもその考えが首尾一貫しているというか「正常」なので、確かに外見は少々異形ですけど、精神的にはただの人に過ぎない感じがします。
同様に、鉄砲に撃たれてエボシを恨んでるナゴノカミや、人間の行為を恨んでるオッコトヌシは、「正常」というか、わりと「常識的」であるがゆえに「神的」ではないですが、そうしたナゴノカミやオッコトヌシの恨みに憑りついた「タタリ神」(黒紫のうねうねしたやつ)は、「神的」だといってよいと思います。つまり、「とにかく暴れること」、「関係ない人を襲うこと」、「関係ないアシタカに呪いをかけたりすること」、といったよくわからないところが「神的」なのだと思います。(もちろん、「よくわからない」というだけではだめで、大前提として、圧倒的な力の発現だ、ということが必要です。)
シシ神について、イノシシたちは自分たちの「守り神」だと思っていたりしていて、モロに、シシ神はそういうものではない、「そんなことも忘れてしまったのか」と、とがめられたりするわけで、さすがにモロはシシ神のことがよくわかっていたようですけど、それだって、「よくわからないものだ」ということがよくわかっていただけのことです。
シシ神殺しについて
最後、サンが「シシ神さまは死んでしまった!」と言ったのに対して、アシタカは、
「シシ神さまは死にはしないよ。生命そのものだから…生と死とふたつとも持っているもの…わたしに生きろといってくれた」
と言うわけですけど、サンが具体的なシシ神(ダイダラボッチになったり、人面鹿みたいな姿で水の上を歩いたりするシシ神、要するに、具体的なヒエロファニーとしてのシシ神)の話をしているのに、アシタカは原理みたいなものとしてのシシ神の話をしています。
で、神殺しというのは、実にそういうことなのだろうなあと思いました。
前に書いた「見えない宗教」化の問題ですね。
つまり、アシタカは、さっきまでそこにいた、具体的に現れているシシ神そのものではなく、シシ神の「意味」の話をしているんですね。神さまというのは、その辺をうろうろしているようなものではなくて、「宇宙に遍在する生命エネルギーのことだ」とかなんとか。その辺をうろうろしているような神さまは「胡散臭い」もので、「本当の神さま」は、直接は見えないけど「信仰心」かなにかでだけとらえることができるものだ、というような考えにつながる考え方だと思います。(そのへんをうろうろしている、というのは、さくらももこの『コジコジ』の言葉です。)
別に、そういった捉え方を悪いというつもりはありませんし、アシタカがおためごかしを言っているというつもりもありませんが、それでもやっぱり、エボシやジコ坊よりも、アシタカがいちばん決定的な「シシ神殺し」をやってしまっているように思えます。
シシ神が「命そのもの」なのは間違いないことですが、重要なことは、そのような「命そのもの」が、シシ神という具体的な形をとって現れているということであって、具体的に現れているということこそが「生きている」ということなわけで、だから、そうした「現れ」(ヒエロファニー)がなくなってしまったのだったら、サンがいうように「シシ神は死んだ」のだと思います。このように「現れ」を失った神のことを、宗教学ではデウス・オティオスス(暇な神)と言います。
一般に「暇な神」というのは、世界そのものを作った神さまのことで、作られた世界(コスモス)を運営する神さまはまた別にいるので、一度世界が出来てしまうと、世界を作るような根本的な神さまは暇になってしまうという理論です。古事記だと、別天つ神の三柱とか、最初に出現してすぐに身を隠したと言われていて、後にもほとんどエピソードがないことから、後世になって挿入されたという説などもあるわけですけど、エピソードのなさはデウス・オティオススだからだともいえるかもしれません。
コスモスを運営する神さまというのは、どちらかというと文化的な神さまで、農耕神であるとか、鍛冶神であるとか、政治的な統治をする神さまであるとかですが、イノシシたちがいう「守り神」というのもそういう神さまです。つまり、ある意味で「人間に都合のよい神さま」ということだと思います。あ、そういえば、シシ神は夜はダイダラボッチとしてその辺を歩き回っていますが、ダイダラボッチというのは世界を作った原初的な巨人のことです。
アシタカは、「森と人間が争わずにすむ道はないのか?」とか言っていますが、これは要するに、「人間」と「神さま」が棲み分けをして、人間は神さまの領域に手を出さないから、代わりに神さまも人間の領域に入ってこないでください、という取引をすることになると思います。
はっきりいってしまうと、その辺をうろうろしているような神さまは迷惑だから、あんまり人間のそばには出てこないでください。その代わりちゃんとご飯を差し上げますから。ということですね。
常陸国風土記に、ヤハズノマタチという人が出てきますが、彼はそのような取引をヤツノカミという神さまとした人です。ヤツノカミというのは、ヤツ(ヤチ・谷津・谷地・谷内、川で削られた低湿地のことで、田んぼにするのに適している場所)の神さまで、形は蛇で頭に角があるとされています。で、あるときマタチという人が、ヤツを開墾して田んぼを作ろうとしたんですが、ヤツノカミがたくさん現われて開墾の邪魔をしました。マタチは怒って、鎧を着て鉾をもってヤツノカミを山まで追い払って、そこに標を立てて、「ここに神社を立ててわたしがあなた方をお祭りする。その代わり、ここから下は人間の土地にするから、以後勝手に入ってくるのは許さん。」と言って、ヤツノカミと人間とが「争わずにすむ」方法を決めたという話です。(日本古典文学大系『風土記』p.55)
あるいは、延喜式祝詞にある「祟り神を遷しやらう」(遷却崇神)という祝詞は、人の居住地のそばに現われた「祟り神」に対して、「ここはあなたにとってあまりいい場所じゃありません。もっと自然が豊かできれいな場所に移った方がいいですよ」的なことを言って神さまに移動してもらうという祝詞です。
そういう話はたくさんあって、これは要するに、人間の文化がだんだん発達してきて、人間の世界がそれだけで自律したものになるにしたがって、よくわからない神さまのようなものが実際に現われると不都合なことが多くなってきたので、人間の領域の外に神さまの領域を作って、そっちに行ってもらおうとしているわけですね。
で、そうするとだんだん、人間の領域内には神さまが現れなくなってくるわけですが、これは神さまを「見えない」ものにしていこうとする過程です。そして、これがもっと進んでくると、実際に神さまはめったに現れないもの(見えないもの)になるから、「見えないということは、いないんだ」ということにもなっていくわけですね。
とはいえ、実際に「見える」人は、「見えないからいない」というようなことを言うわけはないので、そのように言う人は、本当に「見えていない」からそう言うわけですね。
で、彼がどうして神さま的なものを「見る」能力を失ったかというと、アシタカがやったように、「見える神さま」の「本当の意味」を把握するようになったからで、つまり、神さまをよりはっきりと(合理的に・概念的に)把握したからこそ、実際のヒエロファニーは起こりにくくなるという仕組みがあるのだと思います。
もののけ姫のテーマ的な話
もののけ姫の世界では、シシ神と人間の対立が問題になっていますが、「自然」の神さまであるシシ神を、人間の文化が殺すという構図ですね。
しかしながら、そのような場合、ふつうは、文化的な神さまがナチュラルな神さまを殺すという形になるほうが自然だと思います。例えば、ヤマタノオロチを退治するスサノヲとか、ティアマトを倒すマルドゥクとか、ティターン神族を倒すオリンポス神族とか、プルシャを解体するヴェーダの神々とか、そういう話ですね。
つまり、文化というのも、もともとは人的なものではなくて、起源的には神的なものだったということですけど、『もののけ姫』にそういう視点がなかったのは(たとえば、たたらの神とか鉄の神とか剣の神とかが出てこない)、見る人が現代人で、やっぱりテーマ的に「見えない宗教」化が重要な問題だからということなんでしょうかね。
それか、宮崎監督には、ナチュラルな神さまは神さまとして感じられるけれど、文化的な神さまは神さまとして感じられなかったからということでしょうか。そうかもしれません。トトロでもナウシカでもラピュタでも、神さま的なものというのはナチュラルなもので、文化というのは基本的にそれと対立するものとして描かれていますからね。(ナウシカの漫画版の神聖皇帝なんかは文化的宗教っぽいです。)
自然に対する宗教体験から、いきなりヒューマニスティックな文化(俗なる文化)に接続していて、あいだが抜けているというか。
それはともかく、そのような「文化的な神さま」対「ナチュラルな神さま」の話だったら、ナチュラルな神さまは殺されるにしても、その殺されるというドラマにおいて生きつづける(具体的にはそういうコスモゴニーの神話において生きつづける、つまり、殺された神さまの死体から「世界」が作られる)わけですけど、もののけ姫の場合は、「人間の世界」についてのコスモゴニックな話でないわけではないですが、どうもシシ神が引退してデウス・オティオススになって、人間の世界がはじまりましたというような歴史的な話になってしまっていて、そのへんはわたしとしてはけっこう不満ですね。
この場合、神的なものが取り戻されるのは、「あの世」とか、「形而上的世界」においてであって、シシ神さまが死んでしまったこの世では、もうあのように具体的に、「この世界」において「聖なるもの」が現れることはなくなってしまったのだ、といっているような気がします。(もっとも一番最後に、コダマだかスダマだかがカタカタしているので、全くそうなってしまったってわけではないんでしょうけど。)
アシタカが、「シシ神は死んでいない」とか言ってるから、よけいそういう感じがするんですよね。シシ神を殺して、その体から世界が出来たというような「伝統的な」パターンを踏襲している話だったら、シシ神は「この世界」として生き続けているという話になるわけですけど、どうもアシタカの解釈では、シシ神が「形而上」的世界に行ってしまったような感じがしてしまいます。もちろん、アシタカが、「この世界」の根本原理こそがシシ神だから、この世界があるかぎりシシ神は死なないと言いたいのだろうということはわかるんですけど。やっぱり言い方がよくない気がします。アシタカと比べると、単にシシ神を殺して人間の世界を作ろうとしていたエボシや、首を持ち帰ってその力で世界を刷新しようとしていたジコ坊の方が、シシ神に対して真摯に向き合っているような気がするのです。これはわたしが初見の時から感じていたことで、なんかアシタカって、きれいごとを言ってるというか、胡散臭い感じがするんですよね。
とはいえ、これは趣味の問題なので、別に『もののけ姫』に文句があるというわけではないです。現代の日本では、神さまというのはそんな感じのものと思われているんだろうなということですね。
宮崎監督は、そういう失われてしまった「神的なもの」に対して、彼なりにたいへんノスタルジー(楽園のノスタルジー)を感じているんだろうなと思います。で、そうしたノスタルジーにおいて、「神的なもの」はこの世に現れているわけですし、そもそも『もののけ姫』を見ると、実際に生きているシシ神を「見る」ことが出来るわけで、ですからお話の中では、シシ神は死んでしまって、それ以後シシ神がいない世界が始まったと語られているわけですが、実際のところは死んでしまったわけではない、ということなのでしょう。これは『もののけ姫』のコスモゴニックな側面だと思います。
つまり、毎年金曜ロードショウで『もののけ姫』を見ている限り、シシ神は定期的に蘇る(永遠回帰)ということですね。
で、それだったらまあいいか、と、最近は思うようになりました。
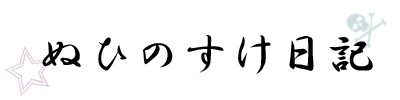
dh3z7m